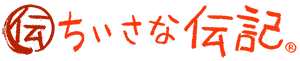野島久雄さんの「思い出作りを考える」のPDFはこちらでご覧いただけます。
野島さんのことはネット検索で見つけたのですが、「思い出工学」という研究ジャンルを提唱されていて、これがなかなかに興味深い。それなりに見つけられるところは一通り読みました。その中の一つが「思い出作りを考える」PDFです。
身に沁みるところが多く、機会を無理やり作ってでもお話を伺いたいなぁ、と思っていたのですが、2011年にお亡くなりになられていることを知りました。56年生まれなので、55歳。今の私と同年代。悲しい。
以下、PDFを要約しながら独り言のようなものを。
・・・・・・・・・・・・
○思い出とは?
「思い出」は、記録や記憶を手がかりにして、自分が作り出す「物語」。それは、事実でなくてもよい。過去のみに関わるものでもない。今の私を形作るものであり、未来の自分を方向付ける情報でもある。
○記録の手段として、写真・スライドショー・ビデオの違いを比較した表。
「典型的な会話」の欄がいい得て妙。

・・・・・・・
○写真アルバムの変遷(『』内は要約)
『家族の写真アルバムは、高度成長期に始まる。撮影する機会は決して多くないので、アルバムに貼って整理することができた。 ナカバヤシ「フエルアルバム」の発売は1968年。写真の枚数が増え始めた時代の証。 80~90年代になると、写真の枚数が増えすぎ整理が追いつかなくなる。90年代後半からはデジタル化により、プリントは少なくなっていくが、撮影枚数は激増し、整理が追いつかなくなる。』
思い出せば、デジタルカメラの直前までは、使い捨てカメラ全盛で、APSカメラというのもあった。APS(アドバンスドフォトシステム)は、ネガにデジタル情報を記録でき、カートリッジごと保存するという、へんてこりんなシステムだった。あんまり普及しない内にデジタル化が急速に進んでしまったけれど、デジタルカメラのセンサーにAPSサイズがあるところを見ると、メーカーの人たちはその当時から、APS→デジタル化を想定していたのだろうか。と思うと、なかなか曲者ですなぁ。
使い捨てカメラ全盛の頃は、女子高生の必須アイテムにもなっていて、当時の女の子たちはネガフィルムは現像後はごみ箱に捨てていたという話もあった。必要なのはプリントだけ。ネガなんて何が写っているのかわからないし、再プリントもしないのなら、「捨てる」のは極めて合理的といっていいんだろう。写真を仕事にしていた私などには論外ではあったけれども。
しかし、「再プリント」なんて本当にやらない。話はズレるけれど、デジタルRAWデータ(生データ)を残しておき、将来の技術で再プリントするなんてことも時々聞くけれど、現実的にどうなんだろう。フィルムもデータも、無いよりは有った方がいいに決まっているけれど。いや、本当に有る方がいいんだろうか・・・。
ともあれ、家族の写真アルバムが実家にたくさんある、という方は多いと思うけれど、高度成長期に子育てをした世代特有のもの、と考えてよいと思う。狭く考えると、1960~80年くらいの20年間。この間の日本人の家族の記録が、これに凝縮されているわけで、これは家族の思い出としてだけでなく、社会的価値のある財産ではないか、と思う。
・・・・・・・・・・・・
○思い出の危機
デジタル化によって、プリントが不要になり、スペースも少なくて済み、一石二鳥みたいな話だったけれど、その実態は何がどこにあるのかさっぱりわからなくなっていたり、ハードの故障で一切合切のデータが無くなったり、とか。昨今のクラウドサービスは、すごく優秀で便利そうだけど、いずれ課金されてお金を払い続けなければならなくなりそう。余裕のある人はすごくいいんだろうけれど、世の中全般的には果たしてどうなんだろう。
というわけで、まとめは次のように。
『 先に述べたように、思い出づくり研究所の取り組みは始まったばかりであるが、この情報過多の時代に おける思い出を保存し、活用するための仕組みを考えていきたいと思っている。さらに、思い出をフォトブ ックのような形にし、その中に価値を見いだしていくためには、そのフォトブックを見せる相手、フォトブッ クの中のストーリーを聞いてくれる相手の存在が重要になる。私たちはその人に見せようとして、思い出 をまとめるのであり、その人に語ることによって思い出はさらに価値を持っていくのである。そうした語り は、おそらくはまずは身近な人、家族や友人に向けられるはずである。フォトブックを通した思い出の語 りが、この情報化・個人化が進む中での人間関係の再構築につながる一助となればと考えている次第 である。 』
まさに我が意を得たりなんですが、最近になって氏のことを知ったのが悔やまれます。
(久門)