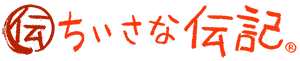オリジナルプリントを介した写真の場を構築する『P.G.I芝浦』
会社概要
'79年春、写真展「米国西海岸の写真家たち」を皮切りに虎ノ門にフォト・ギャラリー・インターナショナルとして開館。以後、「ファインアートとしての写真」を旗印に、オリジナルプリント販売の他、作品の良質な展示や永久保存を目的とした各種用品の開発や普及も行う。'95年にP.G.I芝浦が開館し、2000年に全機能を移転。(取材当時)
写真ギャラリーの匂い
山手線田町駅から徒歩20分弱。お世辞にも気軽に立ち寄れるとは言いがたい距離を歩く。東京湾は目と鼻の先。風向きによっては、潮の匂いを感じることができる立地。洒落たビルの一階と二階がP.G.I芝浦のギャラリーである。
取材日に開催されていたのは、フランコ・メノン氏の写真展「ペシャワール」。全紙大のモノクロプリントをガラス越しに見ながらドアを開けた途端、いつか毎日のように感じていたはずの懐かしい匂いをかすかに感じたのだった。海外から届く木箱、その中の緩衝材。無酸性のミュージアムボード、接着剤やテープなどなど、写真作品を写真作品たらしめるためのさまざまな用具たちが渾然一体となった匂い。むろん、写真作品にも、さまざまな用具にも、匂いなどあるはずがないのだが。
「写真ギャラリーとは、作品を展示できる空間があってこそなのですが、その本質は形のないものです。」
とは、かつて虎ノ門にあったフォト・ギャラリー・インターナショナルの創立から現在にいたるまで、およそ四半世紀をディレクターとして活動し続けてきた山崎氏の、一つ目の謎かけである。
「写真作品とは、作家の表現媒体であると同時に、一つの作品自体があらゆるものを包み込む全体といってもいいでしょう。」
これが二つ目の謎かけ。


「オリジナルプリント」の意味
P.G.Iが扱う写真作品を示す最も適当な言葉といえば「オリジナルプリント」であり、言葉を加えるなら「ファインプリント」となるはずだ。オリジナル【original】とは、特に、美術品や文芸作品の原画や原作を指すけれども、しかしこのように意味を限定しては、P.G.Iの目指すプリントのニュアンスから少しずれる。なぜかというと、この言葉には、「永久保存を目的とした処理を施した、良質のプリント」といった意味が抜け落ちるのである。だから、ファインプリントという言葉を加えておく必要がどうしてもある。
では、ファインプリントとは何か? ファイン【fine】は、美しく立派なさま、見事なさま、微細で精巧なさま、であって、単に「良質の」といい変えてよい。芸術や美術を意味するアートの前につけて、ファインアートといえば、「良質の芸術・美術」という意味になることからも、およその想像はつくはずだ。
ただ、ここで少し留意しておかなければならないのは、芸術や美術でいう良質とは何か? という極めて恣意的な問題である。もとより自由な精神のなかに息づくはずの芸術や美術には、いわゆる良質でない別次元の良質といった概念が含まれる。だからこそ、一歩間違うと、泥沼に落ち込むことになりかねない。
しかし、「永久保存を目的とした・・」という言葉から予感できるように、P.G.Iの作品群を一瞥してみるだけで、重奏低音のように流れる写真の伝統というものを感じざるを得ない。これは、現代の新鋭作家の作品のなかにさえ感じるニュアンスであって、こここそに、P.G.Iが旗印にしてきたという言葉、「ファインアートとしての写真」の意味がはっきりした形をとって現れる。




写真の幸福な場所
虎ノ門にフォト・ギャラリー・インターナショナルが会館した’79年当時、オリジナルプリントおよびファインプリントという言葉は、ほとんど知られていなかった。写真専門の美術館など国中探してもなかった時代である。写真作品を扱う公共の写真美術館、川崎市民ミュージアムの会館は’88年、横浜美術館は’89年、東京都写真美術館第一次会館は’90年の出来事である。
「写真ギャラリーが無形であるというのは、つまり、ここが写真作品を通して人と人がつながる場だということです。一つの理想をいうなら、1平方メートルの空間に最高の作品が一点だけあって、その作品を感動のもとに共有し合える関係を創造したい。さらにいえば、遠い将来に渡って人々の記憶の中にその感動が刻まれ続けていて欲しいのです」
芸術家が人々に求めるのは作品に関する感動だとするなら、p.g.i.というなの写真ギャラリーは山崎氏の作品の一つに数え上げられるだろう。そして、p.g.i.で扱われる作品の作家たちを一括りにして、シリアス写真家と呼ぶことが許されるなら、彼らは一枚一枚の印画紙に魂を焼き付けることのできる魔法使いなのであろう。彼らにとって写真という作品は、決してイメージなどという言葉で語られるものではない。
作品が作家の表現媒体であると同時に、一つの作品事態があらゆるものを包み込む全体になりえるのは、つまりこういう地平においてである。
「たとえば広告写真家と呼ばれる人々の中にも、このギャラリーで作品を扱っている作家がいます。仕事の作品は一線を引く人もいれば、仕事の延長線上に作品が位置する人もいます。考え方はそれぞれでいいのですが、ただ、一点のプリントの製作過程全てに責任を負えるかどうか、が最初のハードルになります」
とりわけ写真のデジタル化によって、写真家のオペレーター化やエディター化といった現象がますます進行しつつある現在である。だからといって反旗を翻らせれば事足りるとは決して思えないほど状況は深刻なのだが、写真が芸術だと胸を張って言い続けることを可能にするためにも、今こそ、オリジナルプリントないしファインプリントの意味を、私たちは私たちなりに考え、それを共有できる場を確保しておかなければならないはずだ。